本サイトの2025年ロードバイクブランド格付けTier総合 第16位、B+ランクに輝くのがイタリアの老舗ブランド・ビアンキ(Bianchi)。ステータス性7、実績7、ブランド人気8、希少性2、羨望性5で合計29点。点数だけ見ると「そこそこ」なのに、日本では老若男女問わず、異常なまでに愛されている。
街に出ればチェレステだらけ。ユニクロとコラボして服まで染め上げ、カフェ前の駐輪場では同じ色の群れが大発生。まるで“ビアンキ動物園”状態だ。
そんな混沌の中で最も目立つのが、エントリーモデルに跨り「俺もビアンキ乗り!」とドヤるロードバイクおぢ──通称“おぢンキ”。走力は初級ローディ、財布もそこそこ、でも心だけはジロ・デ・イタリアに参戦中。
全身チェレステで広告塔と化すその姿は、痛々しいようで実はめちゃくちゃ幸せそう。今回は、そんなおぢンキという珍獣を徹底的に観察していく。
関連リンク:2025年ロードバイクブランド格付けTier総合 第16位 ビアンキ(Bianchi)
ビアンキの自転車の魅力とは
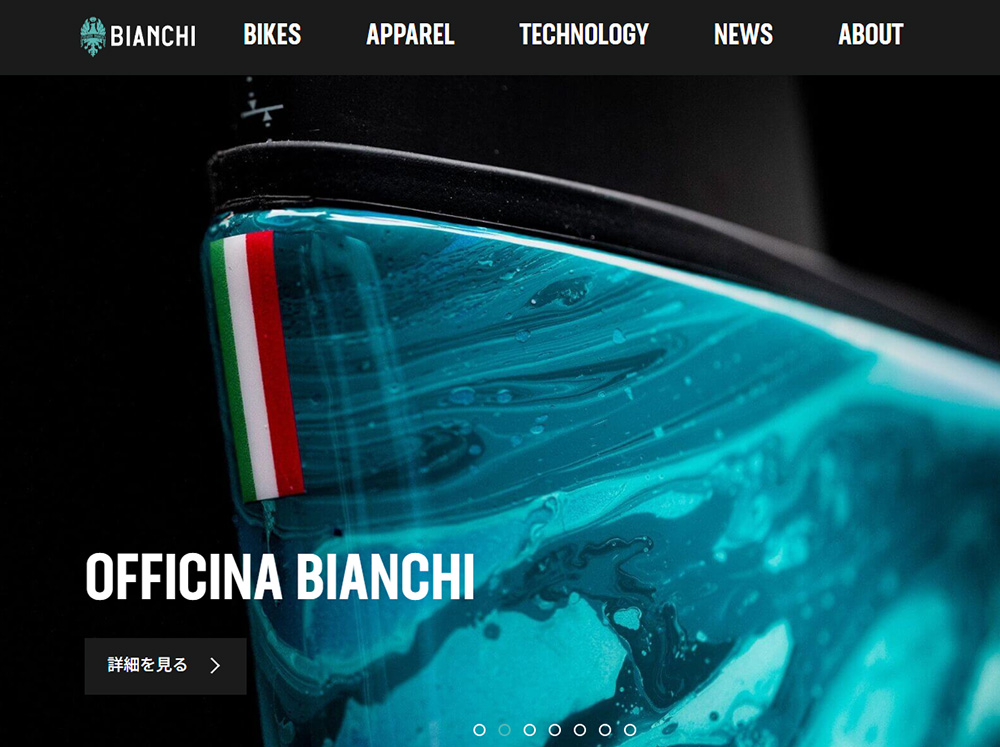
ビアンキの魅力は疑いようがない。ハイエンドモデルはプロレースで結果を残し続け、性能・技術ともに一流。世界中のトップライダーが信頼を寄せる“本物”のブランドである。
──が、ロードバイクおぢがビアンキを選ぶ理由はそこではない。おぢにとって重要なのはカーボンの積層設計でもエアロ性能でもなく、「チェレステであること」。結局のところ、おぢの心を射抜くのは伝統や実績よりも、水色に塗られたフレームが放つ“俺もビアンキ乗り”という錯覚なのである。
130年以上の歴史とチェレステカラーの魔力
ビアンキは1885年創業。ロードバイクブランドとしては世界最古のメーカーであり、その長い歴史は「伝統」という言葉で片づけられないほどの重みを持つ。プロレースの舞台でも幾多の名選手を支えてきた実績は、本物の証そのものだ。
しかし、多くの人がまず惹かれるのは性能よりも“色”だろう。ブランドの象徴であるチェレステカラーは、単なる水色でも青緑でもなく、時代やモデルによって微妙にトーンが異なるのに、なぜか全部まとめて「これぞビアンキ!」と感じさせる魔力を持つ。
おぢたちにとっては「俺のフレームはチェレステだ」という一点こそがステータスであり、歴史や技術の積み重ねよりも先に「色で勝ち」という謎の勝利感を得てしまう。130年の歴史とチェレステの魔力、その合わせ技が、今日もまた新たなおぢンキを生み出しているのだ。
ロードバイク・クロスバイク・E-BIKEなど幅広いラインナップ
ビアンキといえばロードバイク。特に Oltre(オルトレ) や Specialissima(スペシャリッシマ) といったハイエンド機は、プロの舞台で磨かれ続ける本格レーシングモデルだ。性能も歴史も一級品で、ブランドの看板を支える存在といえる。
しかし実際にはクロスバイクやE-BIKEなど、多彩なジャンルを展開しており、「自転車総合ブランド」としての顔も持つ。
その結果、街中でも「通勤用クロスがチェレステ」「E-BIKEで休日サイクリングがチェレステ」など、どのジャンルでも“色の暴力”が炸裂する状況に。若者はクロスで爽やかに、シニアはE-BIKEで悠々と、そしてロードバイクおぢは「俺もプロと同じブランド」とドヤ顔──ターゲット層は違っても、結局みんなチェレステに吸い寄せられていく。
こうしてビアンキは、レースシーンから通勤カバン掛けの駐輪場まで、幅広く浸透。もはや「ロード専用ブランド」ではなく、「チェレステ専売ブランド」と化している。
日本市場での人気と独特の存在感
日本におけるビアンキ人気は、もはや「異常」と言っていいレベルだ。ロードショップに行けば必ずチェレステが並び、河川敷サイクリングロードでは5分に1台はすれ違う。まるで「日本限定チェレステ祭り」である。
ユニクロとコラボしてカジュアルウェアにまで染み出したり、バッグやリュックにロゴを載せて通勤・通学層まで取り込んだりと、その存在感は自転車の枠を軽く越えている。
その一方で「とりあえずビアンキ買っとけば間違いない」という謎の信仰も広がり、実際には性能やグレード差を理解せずに“チェレステだからOK”で購入するおぢや学生が続出。結果として、プロユースのトップモデルとエントリー完成車が同じ色で並ぶという、他ブランドにはない独特の混沌が日本のビアンキシーンを形作っているのだ。
おぢンキとは?〜エントリーモデルでドヤぁ!~
ビアンキと聞けばトップレースで活躍する名機を思い浮かべる人も多いだろう。しかし日本のサイクリングロードで頻繁に目撃されるのは、オルトレでもスペシャリッシマでもなく、エントリーモデルのビアンキを誇らしげに駆る中年男性たちだ。
エントリーモデルの価格帯は10万~30万円ほど。薄給なおぢでも多少無理をすれば変える価格帯なのだ。
彼らは「俺もビアンキ乗り」という事実だけでテンションが最高潮に達し、カフェ前の駐輪場ではまるで勝者のようなドヤ顔を決める。その姿こそが“おぢンキ”。速さや脚力ではなく、チェレステという色に全てを託すロードバイクおぢの最終形態である。
エントリーモデルでも「ビアンキに乗っている=プロ気分」なおぢ
おぢンキとは何者か。端的に言えば、エントリーモデルでも「ビアンキに乗っている=自分はもうプロと同列」と錯覚してしまったロードバイクおぢである。
フレームがチェレステであれば、それだけでジロ・デ・イタリアの舞台に立った気分になり、エントリーモデルのVIA NIRONE 7やARIA、SPRINTなどにまたがりながら「ポガチャルと同じ空気を吸っている」と真顔で信じてしまう。コンポがSORAでもティアグラでも関係ない。色さえ合っていれば心の中ではワールドツアー選手なのだ。
つまりおぢンキの定義とは、「ビアンキに乗っている」という一点を根拠に、実力以上のステータスを背負い込む中年ライダー。その勘違いっぷりが痛々しくも愛おしいゆえに、ロード界隈で語り継がれている。
おぢンキ誕生の背景:ブランド神話とステータス欲求
おぢンキが誕生した最大の理由は、ビアンキというブランドが背負ってきた「神話」である。1885年創業という長い歴史、数々の名選手の栄光、そして唯一無二のチェレステカラー。この三点セットは、ロードバイクおぢの心を一瞬でわし掴みにする。
さらに厄介なのは「俺もビアンキ乗り」という事実そのものが、彼らにとって立派なステータスになる点だ。エントリーモデルの完成車であっても、「ほら見て、この色。プロと同じだろ?」と胸を張れる。まるでブランドの魔力を借りて、自分まで格上げされたように錯覚するのだ。
要するにおぢンキは、ブランド神話にすがり、チェレステを身にまとうことで「俺もロード界の住人だ」という承認欲求を満たしている存在。性能ではなく物語に酔いしれる──そこにおぢンキの源流がある。
実態:走力は初級ローディ、心はジロ・デ・イタリア
おぢンキの実態を冷静に観察すると、走力はせいぜい初級ローディレベル。平均速度25km/hを維持するのもやっとで、登り坂ではクロスバイクに追い抜かれることも珍しくない。にもかかわらず、心の中ではピンクのマリアローザを狙ってジロ・デ・イタリアを走っている。
カフェ前に自転車を停めれば、チェレステのフレームがステージ勝利の証に見えてくるし、仲間とのグループライドでは先頭交代ひとつで「俺はチームリーダーだ」と思い込む。実際の脚力と妄想の乖離が、ロード界隈でおぢンキを「痛いけど愛すべき存在」にしているのだ。
つまり、おぢンキとは“脚は市民大会ビギナー、心はグランツール覇者”。このギャップこそが彼らの最大の魅力であり、最大のネタでもある。
おぢンキが乗るビアンキのエントリーモデル帯バイク
ビアンキのカタログにはハイエンドからE-BIKEまで幅広いラインが並ぶが、おぢンキたちが群がるのは決まって「手の届くロードバイクの完成車」。性能や素材の違いよりも、「チェレステであること」が唯一の判断基準だからだ。
その結果、サイクリングロードやカフェ前では、ある特定のモデルばかりがやたらと目立つ。ロード界隈ではすでに「おぢンキ御用達リスト」と呼ばれるラインナップが存在し、フレームを見れば「あ、これは典型的なおぢンキ機材」とすぐにわかるほどである。
以下では、ここ10年ほどでおぢンキを量産してきた代表モデルを紹介していこう。ここで挙げるモデルの価格帯はいずれも10万~30万円ほど。どれもコスパに優れ、名車といえば名車なのだが、カーボンモデルでも1,100g以上と、下手なハイエンドアルミバイクよりも重かったり、おぢに乗られることで“ネタ枠”として輝いてしまった悲喜こもごもの存在たちだ。
①VIA NIRONE 7:入門おぢの教科書

おぢンキの登竜門といえば、やはり VIA NIRONE 7(ヴィア ニローネ7)。価格は10万〜15万円台と手を伸ばしやすく、ロードバイクデビューにうってつけの1台だ。
そのお手頃さと「とりあえずビアンキに乗ってみたい」という欲求が見事にマッチし、無数のおぢが最初に飛びつく。結果として、河川敷のサイクリングロードではチェレステのニローネが大量発生し、「レンタルか?」と見紛うほどの光景が広がった。
もちろん性能自体は悪くない。むしろエントリーロードとしては真面目で乗りやすいのだが、問題は所有者の意識。おぢンキにとってニローネは「俺もビアンキ乗りだ」と胸を張るための免許証であり、脚力よりもブランドを先に手に入れた証明書なのである。
つまりニローネは、ロードおぢ界隈における“ビアンキ入門書”。読み始めた瞬間に、本人はすでに物語の主人公気分なのだ。
②IMPULSO:アルミなのにカーボンっぽい、とドヤれる

IMPULSO(インプルソ) は、かつてビアンキのアルミ完成車ラインを象徴する存在だった。2010年代前半〜中盤には「スムースウェルド処理」によって溶接痕が消され、見た目はまるでカーボンフレーム。実際の価格は20万円前後ながら、おぢンキにとっては「アルミだけどカーボンに見える、しかもチェレステ」という三拍子揃ったドヤ機材だった。
現在、このアルミ版インプルソはラインナップから外れており、完全に過去のおぢンキ御用達モデルとなっている。ただし「IMPULSO」の名自体は生き残っており、現行ではIMPULSO RC/PRO/COMPといったグラベルやレーシング系モデルに姿を変えて継続中だ。
つまりインプルソは、アルミロードからグラベルへと“進化”してしまったブランド名であり、古いアルミ版を抱えるおぢンキにとっては「俺のは昔のインプルソだぞ」と語る絶好のマウント材料。今となっては中古市場でしかお目にかかれないが、その「カーボンっぽさでドヤれる」DNAは、しっかりおぢの心に刻まれている。
③ARIA:見た目だけプロ級、実走はカフェ往復

ARIA(アリア) は2017年頃に登場したエアロロード。名前からして風を切り裂きそうだが、実際には「プロっぽく見える完成車」としておぢンキに圧倒的人気を博したモデルである。
特徴はそのシルエット。後方へ寝かせたシートステーとシャープなフレームラインは、一見するとツール・ド・フランスのスタートラインに並んでいても違和感がない。フレーム重量は公式仕様で55サイズ約1,150g(±5g)とされており、特別に軽量というわけではないが、カタログ数値よりも「俺のバイク、見た目エアロでしょ?」という自己満足のほうが優先されるのがおぢンキ流だ。
現実には、アリアに跨がったおぢンキの多くが挑むのはジロの山岳ステージではなく、河川敷からカフェまでの往復30km。エアロ効果を発揮する場面はほぼ皆無だが、駐輪場に停めれば十分に視線を集められる。
つまりARIAは、「プロ級の見た目を手軽にドヤれる入門エアロ」。実走の汗よりも、写真映えとカフェ前での存在感が最大の性能値なのである。
④SPRINT:カーボンモデルでも重量は他社のアルミモデルより重い「名前だけ速そう」仕様

“SPRINT(スプリント)”というモデル名を見ただけで、「俺も速くなるに違いない」と思い込むおぢが後を絶たない。実際の現行モデルはカーボンモノコックフレームを採用したエアロ寄りのオールラウンド機であり、決して悪い性能ではない。
フレーム重量はリムブレーキ仕様でおよそ1,080g前後、ディスク仕様で1,100g程度とされ、数字だけ見ればエントリーグレードとしても重すぎる水準。ただホイールやコンポを乗せ換えるなど鬼カスタムを施せば9kgを切ることは可能なレベルなので、普通に走るには十分すぎる性能だ。
しかしおぢンキの頭の中では、重量や剛性の数値など二の次。SPRINTという響きとチェレステカラーさえあれば、「俺の脚はヤスペル・フィリプセン並み」と勝手に補正がかかる。現実には信号だらけの市街地でゼロ発進を繰り返し、スプリントするのは心拍数だけ──そんな姿こそがSPRINTおぢンキの真骨頂である。
⑤INFINITO XE:ロングライド志向おぢ専用、実態は河川敷

INFINITO XE(インフィニート XE) は「エンデュランス」ジャンルのモデルで、ゆったり長距離を走るための設計思想を持っているという位置づけだ。走行快適性・振動吸収性を重視したジオメトリで、ロングライドを志すおぢたちにとっては理想を語るための“証拠”になりうるバイクである。
重量に関しては、明確な “フレーム単体の公称値” を公式に見つけることは難しい。ただし、完成車仕様のレビューやスペック表から読み取れるところでは、完成車重量はおおよそ 8.5kg ~ 9.5kg あたりのモデルが多く見られる。そこから逆算すると、フレーム自体はカーボン構造で 1,200~1,400g あたりのレンジに収まっている可能性がある(仕様やサイズによって大きく変動する前提で)。
とはいえ、おぢンキ的には重量の話はあくまでオプション。重要なのは「俺はロングライド派」という体裁である。講釈垂れながら河川敷を走り、脚を休めてカフェでモーニングパスタをかじるのが日常。実際には山岳コースなどほとんど走らず、平坦路と河川敷を徘徊するだけ──それでも本人は「今日は150km走った気分だ」と満足してしまう。
つまり、INFINITO XE は“ロングライド志向を語るための鎧”。実態は河川敷専用機材というギャップが、おぢンキの妄想劇場を盛り上げているのだ。
⑥BERGAMO:泣く子も黙るサイクルベースあさひ限定モデル

Bianchi BERGAMO(ビアンキ・ベルガモ)は、“おぢンキ”界の最前線に立つ量産機だ。
アルミフレームにカーボンフォーク、SORAやCLARISを積んだ健気な構成に、チェレステのロゴを貼るだけで「俺もビアンキ乗り」と勘違いしたおぢが全国のサイクルベースあさひで誕生している。価格は優しく、夢はそれなり。だが彼らにとっては“あさひで買えるビアンキ”こそがステータスなのだ。
何よりあさひオリジナルのホイールに標準搭載されるリフレクター(反射板)が泣かせる。
通勤途中の坂で息を切らしながらも「これハイエンドよりコスパいい」と言い張り、SNSではチェレステカラーのサドルまで自慢する。実際にはBianchiのブランド名を持つだけの超量産モデルだが、あさひの店頭で見た瞬間の輝きこそ、彼らにとっての“プロショップ体験”なのだ。
ベルガモは、そんなおぢたちに「俺もプロと同じBianchi乗りの一員だ」と錯覚させる、チェレステカラーの現実逃避マシンである。
おぢンキファッション:全身チェレステコーデ

おぢンキをひと目で見分ける方法は簡単だ。バイクだけでなく、本人の全身がチェレステに染まっているかどうか。それが最重要のドレスコードである。
ビアンキというブランドに乗ることは、彼らにとって単なる趣味ではなく自己表現。だからこそ、頭のてっぺんからつま先までを同じ色で統一するという狂気のセンスが発揮される。遠目から見れば鮮やかなブルーグリーンの発光体、近寄れば「もはや広告塔」としか言えないインパクト。
周囲からすれば滑稽でも、本人はそのコーディネートに酔いしれている。おぢンキにとってのファッションは、速さや軽さ以上に「色で語る」ことなのだ。
ヘルメットからソックスまで全部チェレステ
おぢンキのファッションは「とにかく色を揃える」ことに命を懸けている。まずヘルメットをチェレステに。サングラスのフレームまで水色系で寄せれば、顔まわりからすでに“ビアンキ専属ライダー”の完成だ。
そこに上下のジャージ、グローブ、ビンディングシューズ、そして最後はソックスまでチェレステで統一。もはやカラーコーディネートというより、単なる単色塗装である。
遠目には信号機よりもよく目立ち、グループライドの写真に映れば主役級の存在感。しかし他人の目には「おぢが蛍光ペンになった」としか映らないのが悲しい現実だ。とはいえ、おぢ本人は「ここまで揃えるのが真のビアンキ愛」と信じて疑わず、むしろ誇らしげに胸を張る。
全身チェレステは、実用性や美的センスではなく、「俺もビアンキの一部だ」という自己陶酔の象徴なのだ。
ボトル・サドル・バーテープも統一して広告塔化
おぢンキの執念はウェアだけでは終わらない。愛車の細部にまでチェレステを浸透させることで、「俺のバイクはビアンキそのもの」という錯覚を完成させるのだ。
サドルはもちろんチェレステ、バーテープもチェレステ。さらにボトルやボトルケージまで色を揃えれば、走る広告塔が爆誕する。ここまでやれば視認性は抜群、遠くからでも「あ、あれおぢンキだ」と判別できる。
しかし周囲から見れば「何でもかんでも同じ色にすればいいってもんじゃない」というツッコミ必至。せっかくのカーボンフレームも、高級ホイールも、すべて水色の洪水に飲み込まれてしまう。
それでも本人は大満足。むしろ「これがビアンキ愛の証明」と胸を張るのだから、もはやファッションではなく宗教儀式に近い。
「痛い」と言われても本人は大満足
全身チェレステで武装したおぢンキは、たとえ通りすがりの高校生に「だっさ…」と囁かれようが、仲間から「ちょっと痛いな」と苦笑されようが、まったく動じない。なぜなら本人にとっては「俺はビアンキと一体化している」という圧倒的な満足感があるからだ。
むしろ批判されればされるほど、「分かってないな、これが真のビアンキ愛だ」と勝手に解釈して自己肯定感を高めるのが特徴。駐輪場で浮いていようが、SNSでネタにされようが、本人はチェレステに包まれているだけで幸せなのだ。
おぢンキにとって痛いかどうかは問題ではない。重要なのは「俺はこの色に守られている」という自己陶酔であり、その境地に達した瞬間、彼らはもはや“チェレステ仙人”と化すのである。
ビアンキのバッグ・リュック人気

ビアンキの魔力はロードバイクにとどまらない。いまや街中では、チェレステ色のバッグやリュックを背負う人々があふれている。自転車ブランドのグッズでありながら、ファッションアイテムとして若者や通勤通学層にまで浸透してしまったのだ。
もちろんロードバイクおぢにとってもこれは絶好のアイテム。「俺は今日、自転車に乗っていなくてもビアンキだ」と主張できる便利ツールである。おぢンキたちはバッグを背負うことで、街中でもロード界隈と同じく“チェレステ信仰”を周囲に示そうとする。
つまり、ビアンキのバッグやリュックは、実用性以上に「日常生活にまで色を持ち込む」ための道具。おぢがカフェでドヤるために必携のアイテムなのだ。
チェレステカラーのバッグやリュックは通勤通学アイテムとして人気
ビアンキのバッグやリュックは、単なるサイクルグッズの域を超えて「通勤通学の定番アイテム」にまで昇格してしまった。特にチェレステカラーは、一目でビアンキと分かる発色の良さから、電車内でもオフィス街でも学生街でも異常な存在感を放つ。
ロードに乗らない人でさえ背負っているのだから、その浸透力はもはやファッションブランド級。スーツ姿にチェレステリュックを合わせれば「仕事も趣味も色で貫く俺」、学生が背負えば「青春はビアンキ色」と勝手に物語が付与される。
本来はペダルを回すために選ぶはずのブランドが、荷物を運ぶだけで人気を獲得するのだから驚きだ。だがこの“色の力”こそがビアンキの真骨頂であり、バッグ市場においてもチェレステはしっかりとおぢ心と若者心をつかんで離さない。
街中でも“俺はビアンキ”を背負ってドヤれるおぢンキ外伝
バッグやリュックを手にした瞬間、おぢンキはロードバイクに跨っていなくても「俺はビアンキ乗りだ」とドヤ顔が可能になる。つまり街中でのリュック装備は、おぢンキにとって“自転車に乗らない日の代替ユニフォーム”なのだ。
電車に揺られるサラリーマンおぢが、背中にチェレステを背負った途端、心の中では「通勤グランフォンド」開催中。ショッピングモールを歩く休日おぢは、「ここはツール・ド・アウトレット」と自らに言い聞かせながら誇らしげに闊歩する。
周囲から見れば「ただの派手色リュックのおじさん」でしかないのだが、本人は全力でプロ気分。街中で“俺はビアンキ”を演出できる数少ないアイテムとして、バッグやリュックはおぢンキ外伝の主役を張っている。
ファッションと自転車の境界線をなくすアイテム群
ビアンキのバッグやリュックが面白いのは、単なるサイクルアクセサリーではなく、街中で普通にファッションアイテムとして受け入れられている点だ。もはや「自転車に乗るときだけ使う」なんて縛りは存在しない。
チェレステの鮮やかさは、街の風景の中でも妙に浮き立ち、結果的に「おしゃれに見える」と誤解されやすい。スーツに合わせても学生服に合わせても、そこには確かに“ビアンキ色の物語”が付与される。
こうしてバッグやリュックは、自転車ギアと日常ファッションの境界線をあっさり踏み越えた。ロードに乗らなくても「俺はビアンキ」と主張できるし、逆にロードに乗っていても「俺は日常からチェレステ」と一貫性を演出できる。アイテムそのものはただのバッグなのに、持つ人の心の中では“ファッションと自転車の融合”という壮大なテーマにまで昇華してしまうのだ。
ビアンキのミニベロは今どうなった?

ロードバイクやクロスバイクだけでなく、かつてビアンキはミニベロでも存在感を放っていた。チェレステカラーをまとった小径車は、街乗りユーザーからも「オシャレバイク」として人気を集め、サイクリングロードではロードより遅いのにやたらと目立つという不思議な生き物だった。
しかし、気づけば公式ラインナップからは姿を消し、いまや見かけるのは中古市場や在庫限りの販売品ばかり。「あれ、ビアンキのミニベロってまだあるの?」という疑問が出るのも無理はない。
ここでは、かつての定番モデルから生産終了の経緯、そして現在も細々と街に生息する“おぢ仕様ミニベロ”まで、ビアンキ小径車の変遷を追ってみよう。
かつてはMINIVELO-7/8/10、LECCOなどが定番
2000年代後半から2010年代にかけて、ビアンキの小径車といえば MINIVELO-7/8/10、そしてLECCO(レッコ) などが定番だった。ロードやクロスに比べれば明らかに街乗り寄りのカテゴリーだが、そこはやはりビアンキ。フレームがチェレステに塗られているだけで「オシャレミニベロ」として一躍人気者になった。
当時の大学生や社会人は「通学・通勤にちょうどいい」と購入し、カゴ付き仕様にしても「でも俺のはビアンキ」と強がれる便利アイテム。ロードに手を出す前の“予備軍”から、おぢンキの週末街乗り用まで、幅広い層がこの小径車を選んでいた。
見た目はかわいいのに、乗っている本人の気持ちはジロ・デ・イタリア。速度はママチャリと大差ないのに、駐輪場で「これビアンキだよ」とドヤれるのが最大の価値だった。まさにビアンキミニベロは、当時の“街角チェレステ広告塔”として機能していたのである。
2020年モデルで生産終了、現在は在庫や中古のみ流通
ビアンキのミニベロは、2020年モデルを最後に公式ラインナップから姿を消した。MINIVELO-7や10といった定番シリーズも、LECCOも、すべて静かに幕を下ろしたのである。理由は明確には公表されていないが、世界的にはロード・E-BIKEに注力する方向性となり、日本限定的に人気だったミニベロは切り捨てられた形だ。
その結果、現在市場に残っているのは在庫限りや中古品ばかり。自転車ショップでたまたま見つければ「まだ残ってたのか!」とお宝発見気分になり、中古サイトでは相場が微妙に高騰しているケースすらある。
しかし、おぢンキ的には「希少性が出てきたぞ」と逆にドヤ材料に。実走性能よりも「もう新品では買えないんだよね」と言える一点で、満足度が2倍増しになるのだ。つまり、ミニベロは今や“絶版ドヤり枠”としてロード界隈に細々と生き残っているのである。
ミニベロでカフェに出現する“ミニベロおぢンキ”
ロードに乗らずとも「俺はビアンキ乗り」とドヤりたい──そんな欲求を満たしてくれるのが、かつてのミニベロだった。小径ホイールにチェレステフレームを組み合わせれば、速度はママチャリ並みでも、本人の気持ちはジロ・デ・イタリア。
休日のカフェ前には、ロード集団に混じってちょこんと停められたビアンキミニベロが現れる。その横には全身チェレステのおぢがドヤ顔でコーヒーをすする。走行距離は10kmそこそこでも、本人にとっては「俺は今日ロングライド帰り」なのである。
この“ミニベロおぢンキ”の特徴は、速度や距離ではなく、存在そのものが広告塔化していること。ロード界隈からすればツッコミどころ満載だが、本人は誰よりも満足げ。ミニベロでもチェレステであれば、立派におぢンキとして認定されるのだ。
まとめ:ビアンキは色で生きる、おぢンキはその象徴
ビアンキというブランドの魅力は、130年以上の歴史やプロレースでの実績といった本物の価値に裏打ちされている。しかし日本でここまで爆発的に浸透した理由を突き詰めれば、やはり“チェレステカラー”という唯一無二の存在感に行き着く。
そして、その色の力を最もストレートに体現しているのが、おぢンキたちだ。走力は初級ローディレベル、装備はエントリーモデル中心。それでも全身チェレステで固めてカフェに現れれば、本人にとってはそれがツール・ド・フランスの凱旋シーンに変わる。
周囲から見れば痛々しくても、本人は最高に幸せそう。ビアンキが色で生きるブランドなら、おぢンキはその“色信仰”を体現する象徴的キャラクターだろう。結局のところ、ロードバイクとは速さやスペックだけでなく「乗っていて楽しいかどうか」が大事。そういう意味では、おぢンキこそビアンキの本質を一番正直に表現しているのかもしれない。




コメント